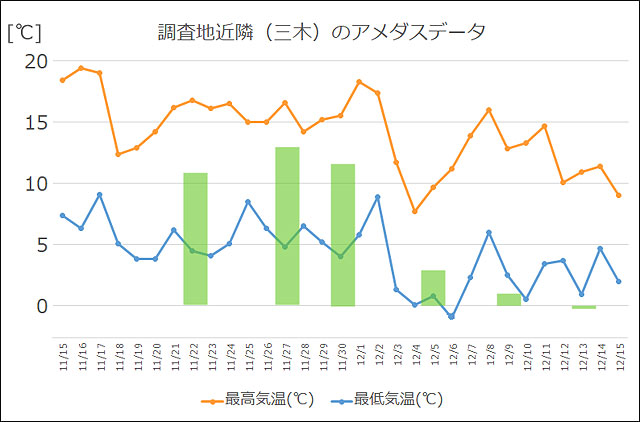今日は朝から快晴で,冬の午後はよく曇るので(今日もそうなった),10:00ごろから調査することにしました.(2.1)というのは,昨日のやり直しの意味です.現地に着くとまだ風は少し冷たい感じでしたが,気温は14℃でした.道の草はまだぬれていましたが,オオキトンボはもう飛んでいました.繁殖活動もまだ行われていました.

▲No.01 オス/No.02 メス:交尾.見つけたのは10:54で,調査の途中だった.▲
まずメスから見ていくことにします.メスは上の交尾態のものも含めて5頭いました.この時期にメスが5頭みつかったというのは,結構多いです.今日は特徴のある翅の破れなどを白矢印で示しました.また上の交尾態のメスは,場所から考えて下の4頭のメスとは異なると考えています.翅の破れがない個体で,下のNo.05個体とは時間的に見て同一ではないと思われます.

▲No.03 メス:左後翅の破れが大きく特徴的である.▲

▲No.04 メス:No.01と左後翅の破れは似ているがよく見ると異なっている.▲

▲No.05 メス:右前翅の先端後縁に小さな破れがあるが,ほぼ破れがない.▲

▲No.06 メス:他の4種と比べても翅の破れの状況は異なる.▲
次はオスです.特徴的な翅の破れがあるものは区別がしやすいですので,それから見ていきます.

▲No.07 オス:4枚の翅全部に破れがあるオス.▲

▲No.08 オス:右後翅が大きく破れているオス.▲

▲No.09 オス:左前翅後縁の大きな破れがある個体.▲

▲No.10 オス:腹部の付け根に大きな傷跡がある.▲

▲No.11 オス:ほぼ完全な翅の持ち主だが右後翅先端後縁に小さな破れがある.▲

▲No.12 オス:翅はほぼ完全な個体.左後翅先端に小さなギザギザが見られるが.▲

▲No.13 オス:翅も体も傷がない.▲

▲No.14 オス:翅も体も傷がない.▲

▲No.15 オス:翅も体も傷がない.体色がまだ茶色味がうすい.▲

▲No.16 オス:翅も体も傷がない.▲

▲No.17 オス:翅も体も傷がない.▲

▲No.18 オス:翅が破れているが,角度的にはっきりしない.▲
以上写真で区別できるのは,No.11までで,No.12以降は同じ個体が混じっている可能性があります.この中で,写真と光の関係かも知れませんが,腹部の茶色化が進んだものと進んでいないものがあるので,少なくとも2個体はいると考えると,11+2で,最低13頭はいたことになります.今日の結果は13頭としておきます.11月の末も近いのになかなかの数が残っている感じです.1回目の10頭以上という結果とあまり変わっていないといえます.
![]()